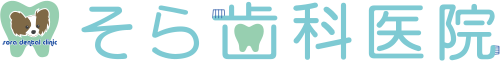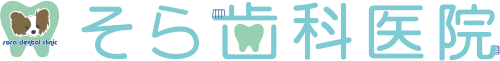江戸川区瑞江そら歯科医院 浜松です。
江戸川区瑞江そら歯科医院 浜松です。題名からして、何を言おうとしているか分からないと思います。
歯となんの関係があるのさ?
建築物や車じゃないんだよと!!
確かにそうなんですが、実は、その役目を果たしている部位が歯周や歯には存在します。
それは、歯根膜と顎骨海綿骨、歯髄(神経が入っている空間)です。
これらは直接ショックアブソーバーとしての機能を果しているわけではありません。
他にちゃんとした役割がありますので、
あくまでも間接的に咬合力を受け止める機能も兼ね備えていると言う事です。
しかし、それら(歯根膜、海綿骨、歯髄)が何らかの変性をきたすとどうなるでしょう?
想像して下さい。
ショックアブソーバーとしての緩衝機能を正常に果たせない時、どこかに無理が生じてきますよね。
その結果、何が起きてしまうのでしょうか?
建物なら壊れますよね、
歯の場合は摩耗したり、修復物が破損したり、最終的には歯根破折が生じてしまうのです。
そして、これは私の想像ですが、咀嚼筋疲労も起きて顎関節症類似症状も発症するのでは
ないかと考えています。
そんな、歯の破折に起因する歯周の変化をきたす方たちが、大変増えてきているように
感じています。
骨硬化症やアンキロ―シス、歯髄腔の退行変性それらを有する人達が増えているのです。
それは、レントゲンを見れば分かりますし、破折した歯を抜歯しようとする時の難易度(癒着)
からも窺い知ることが出来ます。
我々歯科医師は、様々な修復材料に改良を加えたり、修復法を見直しながら咬合力から
歯の破折を防ぐ努力を積み重ねてきました。
しかし、どうしても理屈に合わない事態にも遭遇するにつけ、私は体の局部変化が歯の破折を
誘発しているのではないかと考えるようになりました。
これは、あくまでも私の推測ですので、どなたか研究者の方にメカニズムの解明を
お願いしたいと思っています。
難しい話になりましたが、恐らく間違ってないんじゃないかな~!
おしまい